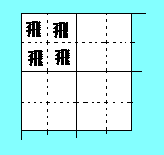
ゲームが子供の頃から好きでした。大好きなゲームを使って子供達を楽しませたいと教員になりたての頃から考えていました。ルールなどオリジナルのゲームを考えらられればいいのですがなかなか難しいので、ここではよく知られたゲームを私なりにアレンジしたものを紹介います。学年始め、時間があったらやってみてください。子供達はみんな喜ぶと思います。
① ビンゴの進化系(5)
③ なるほど・ザ・○○(5)
⑤ ヘビじゃんけん(3)
25マスに数字を書き、それを消していき列をそろえるビンゴ。大人も楽しめるゲームですが、これを学習に応用することも可能です。ビンゴの進化形態をここに紹介します。
ノーマルビンゴ
25マスに漢字、熟語、ローマ字、ことわざ、など学習した語句などを入れる。ランダム(私は、名前プレートを使っている)に児童を選び出し、言わせていく。1列、3列、5列など約束しておき勝敗を決める。
25マスの1マスを4つに区切り、同じ語句等を書かせる。同じ漢字や語句を4回書かせることになるので練習となる。マークする時は、練習した4文字をいっしょにマークする。後はノーマルと同じ。宿題にさせると、いつも忘れる子もゲームに参加したいばっかりにやってくることが多い。
爆弾ビンゴ
ノーマルビンゴの途中(5回に1回程度)で教員が、前もって決めておいた消せない漢字や語句を言う。爆弾が落ちるといってから言うといい。爆弾が落ちた漢字、語句は最後までマークが付けられないので、勝利する確立が少なくなっていく。一発逆転が可能。スリル派にはもってこい。
重要語句ビンゴ(高学年~中学校向け)
教科書の決められた範囲から語句を選び出し、マスに書かせる。自分があたった時に、語句の説明もさせる。説明できない語句はパスとなる。相手が説明した語句にはマークが付けられる。説明の仕方の指導にもなり、知的なビンゴ形態。まとめの時間にやると、評価の少しは足しになる。
物知りビンゴ(おすすめ)
単元の導入などで、子供達の実態把握に使える。植物の単元では、花の名前を書かせたり、家庭科の導入には、キッチンにある物を書かせたり、人間の器官を書かせたり、応用が利く。子供達も試行錯誤するので、脳にもいいと思う。
※ 子供達は、自分ができあがるまで何度もやりたがるが、子供の意見を聞かずに、何人そろったら終わりとか、何人の人が言ったら終わりとか決めておきそれを守ることが重要である。約束の徹底がゲームのポイントとなる。
5つの漢字に共通していることをあてるゲーム。単純なゲームだが、解答方法のシステムを少しアレンジすると、知的で熱中するイベントとなる。
(準備)
教師は、B4版の紙に問題を作っておく。5枚で一組、それが1問。(例)
①10画の漢字
②○年で習った漢字
③門がまえの付く漢字の門構え以外のところ
④にんべんのつくりの部分
⑤クラスの子の名前に使われている漢字 など(やり方)
① 班ごとに図のように並ぶ。
② 担任が5つの漢字・熟語などを黒板に張る。
③ 班の先頭の子に答える権利がある。わかりしだい教師のところにいき、耳もとで答えをささやく。あっていたら、
「大ボンバー」と言い、
2人目は「中ボンバー」、
3人目は「小ボンバー」と言い、3人あたると終わる。④先頭の子を一番後ろに並ばせ、次の問題をはじめる。
※ 間違った時は、その班の一番後ろに並ぶ。そして、先頭になった子に解答権が移動する。
※ わからない時も、教師のところにささやきにくると解答権が移動する。
※ 1位、2位、3位の得点を決めておき、班対抗にすると盛り上がる。
昔はやったなるほど・ザ・ワールドのアレンジ。あのテレビは正解すると場所移動があったが、あれをすると時間のロスになってしまうので、移動はしない。
班対抗で戦う。給食を食べるように机を動かし、問題に対して相談して1つの解答を出す。基本的には3択問題にする。
印刷して不要になったB4版の紙の裏を使う。正解した時の得点を決めておき合計点を競う。点の付け方も、1班だけの正解と、2班正解した時とを変えたりすると逆転がありおもしろい。
(例)
① なるほど・ザ・先生
担任についてのいろいろなことをクイズにしたもの。子供の頃の話題が受ける。うそと思えるようなことほどよい。4月の最初の方にやると担任との距離をぐっと近づけられる。
② なるほど・ザ・フィジー
私の新婚旅行のエピソードを問題にしたもの。旅行の話は子供達はけっこう好き
③ なるほど・ザ・わたし(ぼく)
自分のエピソードや趣味など、人に知られていないことを問題を出し合う。お互いのおもしろい一面が知り合えてクラスが和やかになる。
※ 班員の問題は答えられないようにしておく必要あり。
※ 班員の数が違う時は、一人が2問出題するなど調整しなければならない。④ なるほど・ザ・消防署(社会科見学)
社会科見学など、見てきたことを問題にさせる。社会のまとめとして使える。③と同じような注意が必要。
⑤ なるほど・ザ・雪国 (調べ学習)
調べ学習で覚えたおもしろいことを出題させる。他教科でも応用可能。
昔どこかの局のクイズ番組にあったのを教室でやったら受けたので採用した。同じグループの子の考えを予想したりすることの大切さ、自分勝手はみんなに迷惑をかけるなど協調性を培うのにもいい教材。学活などでやるのがセオリーだが、道徳の最後に挿入することも可能。
<こんなゲーム>
同じ問題をグループの5人が別々に考える。解答した時、同じ答えの組み合わせに点数を付けるゲーム(トランプのポーカーの役を参考にしている)。何問か行ない合計点が多いグループが勝ち。
ワンペア(1組のみ同じ)
ツーペア(同じ解答が2組)
スリーカード(3人が同じ解答)
フルハウス(2人と3人の組み合わせ)
フォーカード(4人が同じ解答)
ファイブカード(5人が同じ解答)<やり方>
① グループを作る5人組みがベスト。
人数がそろわない時は、考えるしかない。
② 5人の机を縦にならべる。
③ 教師が出す問題を考え、紙に書く。(書いた答えは、発表になった変更してはいけない。このルールを徹底することが最大のポイント)
出題例
・科目名を1つ
・曜日を1つ
・さんずいの漢字を1つ など④ 順々に発表させる。教師がグループごとに得点をつけ、黒板にでも書く。
⑤ 同じようにして何問か行なう。
※ 発表のグループの順番やグループの中の発表する子の順番は、問題ごとに変えていった方が良い。とくにグループの最後の子にプレッシャーがかかることを忘れてはならない。
※ 解答を発表させるのは、テンポよくやらせることが重要である。子供達の解答を軽く受け流す程度で良い。ゆっくりやると違った答えを発表した子が苦しむことになる。
一本の道の端と端の2チームに別れて、相手のところに向かっていき、ごっつんこしたところでじゃんけんをして、勝つと相手のところに進め、負けと次の子がスタートして、勝ち続けて、相手の所に行った回数で勝敗を決めるゲーム。道がくねくねしてへびみたいなのでその名がつけられた。それの応用編。道を、遊具でやるとおもしろい。その紹介。タイヤとびあたりでは誰でもやっていると思うが、以下のものではどうでしょう。
登り棒を使って
登り棒をジグザグに進んでいき、ごっつんこしたところでじゃんけん。
鉄棒を使って
鉄棒をジグザグにくぐっていき、ごっつんこしたところでじゃんけん(頭が鉄棒にぶつからないように十分注意させる)。
ジャングルジムを使って
ジャングルジムの2段目あたりを横に進んでいき、ごっつんこしたところでじゃんけん。距離を長くする時には、同じところから右回り、左回りに進むと良い。
⑥ 気分はラスベガス(ルーレットの応用)
ラスベガスのカジノで有名なルーレット。00~36までの数字にお金をかけるゲーム。かけ方が、1/2、1/3、1/4の確率などいろいろあり、その確率によって配当が決まっているというシステムになっています。例えば、赤か黒か(数字にどちらかの色が付いている)のかけ方の場合は、配当が2倍となります。
このシステムを5年算数の「倍数と約数」のところで使ってみました。
1.ルーレットを購入する。おもちゃ屋や100円均一の店にある。(私は、32面サイコロを使ったこともある)
2.偽者のお金(絵が書かれた小さいカードでもOK)
3.かける場を用意する。ここがアイデアなのだが、ただ、数字を並べるのではなくて、「2の倍数」「3の倍数」「36の約数」「3と5の公倍数」などのかける枠を作る。配当は、公倍数や公約数など頭を使う所を高くする方がいい気がする。出る確率に配当を合わせる必要はないと思う。
4.全員を1枚のかける場にかけさせるのは難しいので、5~8人のグループぐらいでやらせるのがいい。親(銀行)をかわりばんこにさせてもいいし、銀行(お金を入れた箱)をグループごとに用意させてもいい。ルーーレットは教師が回した方がトラブルは少ない。また、かけていいカードの上限を決めておいた方がいい。
いわゆるギャンブルなので、いろいろな配慮が必要です。そこのところはよろしくです。絶対に盛り上がる知的興奮を与えられるゲームです。
プールの休憩時間に子供たちがやっている「おせんべ焼けたかな」。単純であるがおもしろい手遊び。
普通は、手のひらをおせんべに見立てているわけだが、指1本ずつをおせんべにみたててやってみると子供たちに必ずうける。裏が焼けないという欠点があるが、指された指を食べたこととして下に折っていく。薬指など折りずらいので子供たちは大騒ぎ。2本、3本と指を曲げていくのはとても至難の技。盛り上がること間違いなし。一度、お試しを。
TBSテレビ「筋肉番付のストラックアウト」のアレンジ。どんな遊びでも使える。1~9の数字を書いたカードやボードを用意して全部を落としていくシステム。回数はその都度教師が設定すればOK!
私がやったことあるのは、1.めんこバトル
2.バトルチップ
3.ダンボールを置いて、バスケットボール次のは、本校の用務技師さんのアイデア。
ジャングルジムにビニールのボードを掛けるようにしてサッカー。
これって結構いけてる。